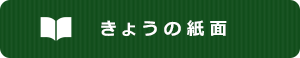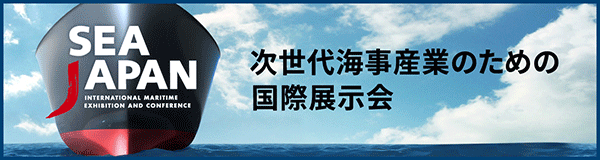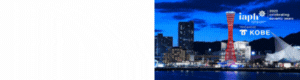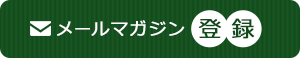- ニュース
- 特集
特集【無料】
2020年2月19日無料公開記事
国際物流総合展特集 ロジ革新で、社会課題の解決へ
日本国内では人手不足が産業全体の課題となる中、SDGs(持続可能な開発目標)の達成などESG(環境・社会・ガバナンス)経営の重要性が増している。また生産・販売のグローバルでの水平分業はますます進んでいる。産業の基盤となるロジスティクスは、それら課題の解決、企業のサポートを行っていくために、ビジネスモデルやサービスを革新していく必要がある。ロジスティクス最新動向を追う。
■インテル日本法人
協業でデジタル化、モデルケース構築
デジタル化した未来の物流の現場では、モノやヒトの動きがデータとして吸い上げられ、それを基にサプライチェーンや企業の意思決定、業務効率化が行われるとされる。データの収集や通信、分析といった領域でのIT技術やコンピュータの重要性はますます高まっていくと見られる。一方、現在の多くの物流現場ではいまだ手作業や人力で行われる業務も多い。半導体大手インテルの日本法人では、産業全体をデジタル化する挑戦に取り組んでいる。各種パートナーとの連携・協業により、ユーザーが利用しやすいハード/ソフトのデジタルツール、モデルケースの構築を急ぐ。
少子高齢化や持続可能社会の移行といった社会問題・企業課題への対処として、デジタル化の取り組みがさまざまな産業で進められている。物流でも国内外でデジタル化が叫ばれて久しく、物流企業にとってデジタル化は最重要の課題の1つとなっている。
特に物流は課題の多い産業だ。倉庫や人員などの物理的アセットを持つ必要があり、生産性を向上させていかなければ、コストとの折り合いがつかなくなる。また昨今では自然災害や不透明な国際情勢など、不確実性も大きくなっており、アセットやリソースをどう最適化していくかは非常に困難となっている。しかし、インテル日本法人の張磊(チョウ・ライ)執行役員インダストリー事業本部長は「ハードルは高いが、逆にデジタル化による効果が大きいのも物流だ」と話す。
インテルではグローバルで、デジタル化の推進に向け、企業や個人が簡便にデータを収集・分析するためのエコシステムを生成する取り組みを行っている。データ収集につながるIoT分野では、さまざまな企業が先進的なソリューションを開発しているものの、実践するには実証や検証、またそのための投資が必要というケースが多い。同社では、Market Ready Solution(以下、MRS)として、パートナーとともにIoTソリューション事例の開発を進めている。ある程度実証済みで、ユーザーが導入しやすい状態のソリューションをパッケージ化。そのラインナップを増やし、紹介・提案することで、企業のデジタル化を促す。
張執行役員は「当社はコンピュータのチップ、CPUや半導体がなりわいであり、産業別の専用機器やソリューションを作る会社ではない。企業がデジタルで課題を解決し、ビジネスを伸ばしていくと、どこかで当社のチップが使われる。ユーザーに対しては中立的な立場で、課題を聞きながら、1つひとつ事例を積み上げていきたい」と話す。
MRSは現在、200ほどの事例があり、物流の事例もある。そのうちの1つが、日本通運がインテルの技術を活用して商品化した、輸送状況の可視化サービス「Global Cargo Watcher Advance(以下、GCWA)」に利用されている。品質輸送のデータを収集する「インテル・コネクテッド・ロジスティクス・プラットフォーム(以下、ICLP)」を活用し、貨物に取り付けられたセンサータグ(子機)が、温度などの各種データを計測し、トラックや倉庫内に設置されたゲートウェイ(親機)を通し、データをクラウド上にアップロードする。そうした輸送情報は関係者間でリアルタイムの把握が可能だ。またデータを蓄積することで、ルートごとの品質の可視化、事故防止などの付加価値ソリューションの提供も可能になる。
日通はGCWAを利用し、医薬品物流のトレーサビリティ・プラットフォームを構築していく。今後、日本では、日本版GDP(医薬品の適正流通基準)が法制化され、より厳格な輸送品質が求められるようになる。GCWAの機器で吸い上げた情報に加え、受発注、決済、所有権移転などのデータを管理する一元的な情報サービスプラットフォームを公開し、製薬メーカー、卸・小売など全体にまたがるサプライチェーンの全体最適を図る。張執行役員は日通の事例について「戦略的な意図を持ったデジタルへの投資の好例だろう。物流と商流の両方でビジネスの仕組みや商習慣を変えるきっかけとなる優れた取り組みだと言える」と協業での取り組みに自信をのぞかせる。
張執行役員はまた、今後の展開について「中立的な立場として情報を集め、パートナー同士のマッチメイクなど橋渡しなどをすることで、物流産業のデジタル化を促していきたいと」話した。
■JILS、「コンセプト2030」策定
ロジスティクスを新たな産業に
日本ロジスティクスシステム協会(JILS)は2030年に向けて目指すべきロジスティクスのあり方や提言をまとめた「ロジスティクスコンセプト2030」を策定した。「デジタルコネクトで目指す次の産業と社会」をスローガンとし、より一層求められる「持続可能性」への対応と、プラットフォーマーの台頭といった産業構造の変化に合わせて、10年後のあるべき姿として描いた「ユートピア」モデルの実現に向けて行うべき提言をまとめている。ここで志向されているロジスティクス像について見ていこう。
今回のコンセプト策定に当たって念頭に置いたのは、環境変化への対応だ。人手不足など社会構造や、B to C/C to Cのモノの流れなど需要の変化、環境面での課題を前提として、これらを克服・解決していくロジスティクスのあり方とはどうあるべきかを議論し、策定した。
コンセプトでは議論のベースとして、2つの異なる将来像を描いている。現在の物流コストの課題といった趨勢が続いたと仮定した「ディストピア」モデルと、情報技術などの活用で課題を解決できる理想的な「ユートピア」モデルの2つだ。
ディストピア編では、資源やエネルギー面での課題、需要予測などから、今後の課題を浮き彫りにしている。国内物流において営業用貨物自動車の需給バランスは、今後、需要量に対する供給の不足が増大する傾向が続き、30年には11.4億トン(需要量の35.9%に相当)が運べなくなる見通しという。
環境問題や人手不足、需要拡大に対し、JILS総合研究所ロジスティクス環境推進センターの北条英センター長は「ロジスティクスが本来志向する“全体最適”を追求していくことで解決を目指すべき」と話す。その上で「ロジスティクス的な考え方をビジネスモデルにすれば、既存の物流やサプライチェーンと異なる新しい産業が生まれるのではないか」という。課題解決の追求とともに、それを解決する新たなビジネス形態を創造していこうというのだ。
それがユートピア編で描かれている。「発展するデジタル化や人工知能(AI)などの情報技術を用い、その恩恵を受けたオープンなプラットフォームを基盤とする全体最適のシステムが“新たな産業部門”を形成している状態」がそれにあたるという。
そこでいう「オープンなプラットフォーム」とはどういうものか。コンセプトにおいてユートピアのロジスティクスモデルは「情報の非対称性を解消することで単一商品やサービスの受給をマッチングしている現状のモデルから、標準化されたコンテナ(フィジカルパケット)を輸送区間(ライン)と結節点(ノード)にダイナミックに流し込む(ルーティング)モデルへ変貌している」としている。モノの流れで言えば、輸送リクエスト者と輸送手段提供者からなるオープンな市場が形成され、それを可能にするソフトウェアプラットフォームを介して、最適な輸送手段の選択・自動化が行なわれることになる。
北条センター長は、そうした市場において「トラックや倉庫などのアセットは公共財として考える必要がある」と話す。物流とデータ共有型のプラットフォームを基盤として、商流や情報流といった多層的な価値を1つのプラットフォームとして提供できるようになれば、新たなロジスティクスを新たな産業と進化させることが可能になるだろうという。
ただ、ここでは、既存のビジネスモデル、つまり輸送力やネットワークで差別化して競争するモデルとの決別を意味する。競合企業同士の協業や連携、また、プラットフォーマーがデータを独占しない形で社会実装する必要もある。果たして、それは可能なのか。
JILSでは実現のための方策を、提言としてまとめた(表参照)。ロジスティクスやサプライチェーンのあり方を見つめ直すとともに、デジタルコネクトやシェアリングのための標準化やルール作りを実行していく必要がある。また産業全体や各社の投資拡大、プラットフォーマーの育成も必要となる。
ただ、これを実行していくための課題として、北条センター長は「経営者の意識改革」を挙げる。「現状のロジスティクスの体制で、地球環境や経済が立ち行かなくなることは明らか。産業や社会のあり方を変えなければいけない。経営者の意識改革、それによる文化の醸成や高度人材の育成といったことが必要だ」と指摘している。それぞれの提言についても、実行に向けた課題は多い。さらに将来迎える大きな課題、まずはその課題を産業全体として認識することが必要となりそうだ。
■日本通運、自動化・IoT技術を実運用展示
東京・江東区に最先端物流センター開設
日本通運は東京・江東区新砂に、IT化や自動化、可視化などを目的とした最新物流システム機器・設備と同社のオペレーションを一体化させた物流ソリューションを集約させた最先端ロジスティクスセンター「NEX-Auto Logistics Facility」を新設する。今年6月の開設予定だ。
物流現場で自動化・省人化設備の導入が求められる中、先端物流機器の導入には、最適な機器の選定、大規模なレイアウト変更、作業フローの見直しのほか、投資資金負担などの諸課題をクリアする必要がある。日通は顧客にとって最適な最先端の物流機器と、同社の「現場力」を融合した新しいソリューション「NEX-Sustainable Logistics on NewStyle」としてシェアリングサービスなどの実現により、お客さまのロジスティクスに関する課題解決に向けた、物流ソリューションを提供していく。
今回の新センター開設には、そうしたソリューションを提示・提案するためのショールームの機能を持たせた。自動倉庫型ピッキングシステム「AutoStore(オートストア)」や最新の自動荷役機器、デジタルピッキングシステム、ITソリューションなどを導入。実際の業務をベースとしたモデルケースを構築。プレゼンルーム、研修センターとしての機能も持たせ、日通の高度なロジスティクスサービスの提供、販売、研究、教育の場として活用していく。
新センターは同社国内最大級の都市型物流拠点「Tokyo C-NEX」に隣接する施設「新砂5号」の3階部分(約3000平方メートル)に開設する。導入する最先端機器・設備は表の通り。今回の機器選定にあたっては、(1)省人化の推進(2)機器同士の接続を重視したという。(1)については、倉庫作業の完全自動化やAI(人工知能)を用いた物流ソリューションへの移行を見据えてのもの。従来は作業スタッフをサポートする機器の導入を進めてきたが、省人化を大く進める機器を採り入れ、半自動化倉庫を実現する。
(2)については、自動化マテハン機器を組み合わせた倉庫オペレーションの構築につなげる考え。倉庫作業の最新事例として、ロボットや自動倉庫の導入事例は出てきているものの、まだそれらを組み合わせて入庫から保管、仕分け、出庫までのフローを構築しているものは少ない。新センターの出庫作業では、オートストアとピッキングシステムのEVE、デジタルピッキングを組み合わせ、効率的かつ省人化した作業フローを構築している。
機器・設備のほか、日通商事や日通総合研究所、ワンビシアーカイブズのグループ会社のノウハウやサービスも組み合わせて、ソリューション、オペレーションを構築。日通総研が提供するデータ集計・分析ツール「ろじたん」や、ワンビシアーカイブズの現場改善プログラムなどを用いて、業務自体の高度化も推進する。ショールームにはグループ会社の紹介コーナーも設置。日通とグループ各社のソリューションを合わせ、お客さまからの相談受付、物流課題を解決する場としても機能させていくとしている。
今回は、アパレル物流に適した高度化・省人化ソリューションを整えたが、施設での取り組みをベースとして、他の産業・品目での先端・次世代物流の研究・構築、営業提案などを進めていく考え。また、次の展開として、新設備の導入やAIを活用した新たなソリューション構築も検討していくという。
■日通NECロジスティクス
電機精密で顧客物流業務取り込み
日通NECロジスティクスは、日本通運と連携し、NECの生産・販売物流で培ったノウハウをもとに半導体業界を中心とした電機精密業界の顧客の物流アウトソース需要の取り込みを進めている。
同社では、大手半導体メーカーの工場内の物流業務を長年受託している実績があり、生産領域に関わるノウハウを蓄積。これらノウハウに加え、半導体産業で求められる温湿度対策、防塵・静電気対策やクリーンルーム・保安基準などの施設環境や製品取り扱いに関わる高度高品質な運用手法を整備。また、これら手法に加え、同社独自で構築している幹線ネットワーク網での輸送を組み合わせることで半導体物流プラットフォームを確立した。
このプラットフォームを活用し、調達・生産・販売まで一貫での受託を進め、日本国内はもとより海外においても10カ国・地域でサービスを展開している。日本基準のトレーニングを受けた専任スタッフが教育・運用管理・改善活動を行い、日本品質で半導体の保管・出荷・配送需要に応えている。
さらに海外では、高付加価値なサービスとして、現地に法人や拠点を持たないが、いち早くビジネスを立ち上げたいという顧客に対し、非居住者VMI(ベンダー管理在庫)サービスの提案を進めている。同サービスにより顧客は生産拠点の移管や販売先国の変更などに素早く対応できるのがメリットだ。
また、前述の幹線ネットワークの活用という点では、国内において「展開物流」と呼ぶ多店舗・拠点への一括納入サービスにも注力。全国・地域など広域の複数拠点に「指定された期限内に画一化された製品群とサービス」で機器類の事前設定から納品・設置・回収までを行うサービスだ。パソコンをはじめ、コンビニのATMやPOSから駅施設の専用端末など、多様な機器を扱っている。同社の輸送ネットワークは、長年にわたり電機精密機器を扱うことで培った高い品質に加え、13年に日通グループとなってから、輸送網を強化。また日通グループのアセット・機動力を活用することで、全国各地で一斉納入・回収したいというニーズに応えられる体制が構築されている。
■商船三井ロジスティクス
海外各地で物流立ち上げ支援
商船三井ロジスティクスは海外各地での保管・配送などの物流立ち上げを得意とする。日本本社のロジスティクスソリューション(LS)部に機能を集約することで、スピーディーかつ高品質なオペレーション体制が構築できる仕組みを整えている。直近では、完成車の整備・点検など付加価値サービスのラインナップも拡充。フォワーディング事業で培ったネットワークを生かし、新興国・地域を中心に事業拡大を狙う。
コントラクトロジスティクス案件では、用地の選定から、スペースや要員の確保、オペレーション構築、その後の運営まで一貫したサポートを提供。LS部の保坂直輝部長は「ニーズに対して、テーラーメイドな物流を作り込めるのが強みだ」と話す。
海外、特に新興国でのロジスティクス構築では現地での人材育成が肝要となる。同社はLS部にノウハウを集中させていることで、世界各地どこでも作業手順書(SOP)やチェック体制の作り込み、作業員への教育・訓練などを確実かつ迅速に行える体制となっている。
付加価値サービスの提供にも力を入れる。昨秋にはフィリピンで大手自動車メーカーの完成車に関わる納車前点検(Pre-Delivery Inspection Center:PDI)サービスの取り扱いを開始した。センターを設け、輸入完成車に関わる水漏れテスト、軽微な修理や塗装、洗車などを含めた高品質なPDIサービスを、輸入通関、一時保管サービスとともに提供している。保坂部長は「自動車産業は裾野も広く、今後も拡大していきたい分野だ。商船三井の自動車船部隊とも連携し、PDIだけでなくサービスパーツなどの部品物流分野の業務にも取り組んでいきたい」と意気込む。
PDIのみならず品目やサービス内容にも広がりが出ている。昨年には米国西海岸で、販売店に納めるコンシューマー商材の取り扱いを開始。自営倉庫を利用し、数千におよぶ細かなアイテムの在庫管理、キッティング、国内出荷(店舗配送およびeコマース)を手掛けている。また直近では、インドネシアのスマトラ島で機械製品の保管・域内配送業務を受託した。部品物流に加え、消費財の取り扱いや、新興地域での国内・域内配送といった分野での拡大も進めていきたいとの意向だ。
■横須賀港
来年、新門司とのフェリー航路新設へ
横須賀港は来年、北九州港・新門司地区との国内フェリー航路が就航する予定だ。国内外でフェリー事業を展開するSHKライングループが運航する計画で、同グループは昨年4月に運航会社として東京九州フェリーを設立。約1万6000総トン級のフェリー2隻を投入し、日曜を除く週6便体制で運航する。片道20時間半と高速輸送体制を構築しており、九州へ迅速な荷物の輸送が可能となる。横須賀市は物流・観光両面での利用促進活動を積極化するとともに、今後、関係機関や事業者などと協議を行い、必要経費を予算に盛り込む方向で調整する。就航に備えて関係する整備を進めていく方針だ。
横須賀港としては国内フェリーの就航に加え、久里浜地区への定期航路の誘致も狙う考えだ。同地区では現在、東京湾フェリーや離島行きの観光船が就航しているが、定期的な貨物航路はシャトルハイウェイラインによる横須賀-大分航路が2007年に休止して以降、存在していなかった。久里浜港地区は東京湾入口に位置するため、浦賀水道航路の速度制限を受けないほか、混雑する都心を通らずに東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道にアクセス可能というメリットがある。今後も圏央道の藤沢-釜利谷間が開通する予定で、北関東方面へのアクセスも改善される。背後圏への輸送利便性を強みに新規船社の誘致を図っていきたい考えだ。
協業でデジタル化、モデルケース構築
デジタル化した未来の物流の現場では、モノやヒトの動きがデータとして吸い上げられ、それを基にサプライチェーンや企業の意思決定、業務効率化が行われるとされる。データの収集や通信、分析といった領域でのIT技術やコンピュータの重要性はますます高まっていくと見られる。一方、現在の多くの物流現場ではいまだ手作業や人力で行われる業務も多い。半導体大手インテルの日本法人では、産業全体をデジタル化する挑戦に取り組んでいる。各種パートナーとの連携・協業により、ユーザーが利用しやすいハード/ソフトのデジタルツール、モデルケースの構築を急ぐ。
少子高齢化や持続可能社会の移行といった社会問題・企業課題への対処として、デジタル化の取り組みがさまざまな産業で進められている。物流でも国内外でデジタル化が叫ばれて久しく、物流企業にとってデジタル化は最重要の課題の1つとなっている。
特に物流は課題の多い産業だ。倉庫や人員などの物理的アセットを持つ必要があり、生産性を向上させていかなければ、コストとの折り合いがつかなくなる。また昨今では自然災害や不透明な国際情勢など、不確実性も大きくなっており、アセットやリソースをどう最適化していくかは非常に困難となっている。しかし、インテル日本法人の張磊(チョウ・ライ)執行役員インダストリー事業本部長は「ハードルは高いが、逆にデジタル化による効果が大きいのも物流だ」と話す。
インテルではグローバルで、デジタル化の推進に向け、企業や個人が簡便にデータを収集・分析するためのエコシステムを生成する取り組みを行っている。データ収集につながるIoT分野では、さまざまな企業が先進的なソリューションを開発しているものの、実践するには実証や検証、またそのための投資が必要というケースが多い。同社では、Market Ready Solution(以下、MRS)として、パートナーとともにIoTソリューション事例の開発を進めている。ある程度実証済みで、ユーザーが導入しやすい状態のソリューションをパッケージ化。そのラインナップを増やし、紹介・提案することで、企業のデジタル化を促す。
張執行役員は「当社はコンピュータのチップ、CPUや半導体がなりわいであり、産業別の専用機器やソリューションを作る会社ではない。企業がデジタルで課題を解決し、ビジネスを伸ばしていくと、どこかで当社のチップが使われる。ユーザーに対しては中立的な立場で、課題を聞きながら、1つひとつ事例を積み上げていきたい」と話す。
MRSは現在、200ほどの事例があり、物流の事例もある。そのうちの1つが、日本通運がインテルの技術を活用して商品化した、輸送状況の可視化サービス「Global Cargo Watcher Advance(以下、GCWA)」に利用されている。品質輸送のデータを収集する「インテル・コネクテッド・ロジスティクス・プラットフォーム(以下、ICLP)」を活用し、貨物に取り付けられたセンサータグ(子機)が、温度などの各種データを計測し、トラックや倉庫内に設置されたゲートウェイ(親機)を通し、データをクラウド上にアップロードする。そうした輸送情報は関係者間でリアルタイムの把握が可能だ。またデータを蓄積することで、ルートごとの品質の可視化、事故防止などの付加価値ソリューションの提供も可能になる。
日通はGCWAを利用し、医薬品物流のトレーサビリティ・プラットフォームを構築していく。今後、日本では、日本版GDP(医薬品の適正流通基準)が法制化され、より厳格な輸送品質が求められるようになる。GCWAの機器で吸い上げた情報に加え、受発注、決済、所有権移転などのデータを管理する一元的な情報サービスプラットフォームを公開し、製薬メーカー、卸・小売など全体にまたがるサプライチェーンの全体最適を図る。張執行役員は日通の事例について「戦略的な意図を持ったデジタルへの投資の好例だろう。物流と商流の両方でビジネスの仕組みや商習慣を変えるきっかけとなる優れた取り組みだと言える」と協業での取り組みに自信をのぞかせる。
張執行役員はまた、今後の展開について「中立的な立場として情報を集め、パートナー同士のマッチメイクなど橋渡しなどをすることで、物流産業のデジタル化を促していきたいと」話した。
■JILS、「コンセプト2030」策定
ロジスティクスを新たな産業に
日本ロジスティクスシステム協会(JILS)は2030年に向けて目指すべきロジスティクスのあり方や提言をまとめた「ロジスティクスコンセプト2030」を策定した。「デジタルコネクトで目指す次の産業と社会」をスローガンとし、より一層求められる「持続可能性」への対応と、プラットフォーマーの台頭といった産業構造の変化に合わせて、10年後のあるべき姿として描いた「ユートピア」モデルの実現に向けて行うべき提言をまとめている。ここで志向されているロジスティクス像について見ていこう。
今回のコンセプト策定に当たって念頭に置いたのは、環境変化への対応だ。人手不足など社会構造や、B to C/C to Cのモノの流れなど需要の変化、環境面での課題を前提として、これらを克服・解決していくロジスティクスのあり方とはどうあるべきかを議論し、策定した。
コンセプトでは議論のベースとして、2つの異なる将来像を描いている。現在の物流コストの課題といった趨勢が続いたと仮定した「ディストピア」モデルと、情報技術などの活用で課題を解決できる理想的な「ユートピア」モデルの2つだ。
ディストピア編では、資源やエネルギー面での課題、需要予測などから、今後の課題を浮き彫りにしている。国内物流において営業用貨物自動車の需給バランスは、今後、需要量に対する供給の不足が増大する傾向が続き、30年には11.4億トン(需要量の35.9%に相当)が運べなくなる見通しという。
環境問題や人手不足、需要拡大に対し、JILS総合研究所ロジスティクス環境推進センターの北条英センター長は「ロジスティクスが本来志向する“全体最適”を追求していくことで解決を目指すべき」と話す。その上で「ロジスティクス的な考え方をビジネスモデルにすれば、既存の物流やサプライチェーンと異なる新しい産業が生まれるのではないか」という。課題解決の追求とともに、それを解決する新たなビジネス形態を創造していこうというのだ。
それがユートピア編で描かれている。「発展するデジタル化や人工知能(AI)などの情報技術を用い、その恩恵を受けたオープンなプラットフォームを基盤とする全体最適のシステムが“新たな産業部門”を形成している状態」がそれにあたるという。
そこでいう「オープンなプラットフォーム」とはどういうものか。コンセプトにおいてユートピアのロジスティクスモデルは「情報の非対称性を解消することで単一商品やサービスの受給をマッチングしている現状のモデルから、標準化されたコンテナ(フィジカルパケット)を輸送区間(ライン)と結節点(ノード)にダイナミックに流し込む(ルーティング)モデルへ変貌している」としている。モノの流れで言えば、輸送リクエスト者と輸送手段提供者からなるオープンな市場が形成され、それを可能にするソフトウェアプラットフォームを介して、最適な輸送手段の選択・自動化が行なわれることになる。
北条センター長は、そうした市場において「トラックや倉庫などのアセットは公共財として考える必要がある」と話す。物流とデータ共有型のプラットフォームを基盤として、商流や情報流といった多層的な価値を1つのプラットフォームとして提供できるようになれば、新たなロジスティクスを新たな産業と進化させることが可能になるだろうという。
ただ、ここでは、既存のビジネスモデル、つまり輸送力やネットワークで差別化して競争するモデルとの決別を意味する。競合企業同士の協業や連携、また、プラットフォーマーがデータを独占しない形で社会実装する必要もある。果たして、それは可能なのか。
JILSでは実現のための方策を、提言としてまとめた(表参照)。ロジスティクスやサプライチェーンのあり方を見つめ直すとともに、デジタルコネクトやシェアリングのための標準化やルール作りを実行していく必要がある。また産業全体や各社の投資拡大、プラットフォーマーの育成も必要となる。
ただ、これを実行していくための課題として、北条センター長は「経営者の意識改革」を挙げる。「現状のロジスティクスの体制で、地球環境や経済が立ち行かなくなることは明らか。産業や社会のあり方を変えなければいけない。経営者の意識改革、それによる文化の醸成や高度人材の育成といったことが必要だ」と指摘している。それぞれの提言についても、実行に向けた課題は多い。さらに将来迎える大きな課題、まずはその課題を産業全体として認識することが必要となりそうだ。
■日本通運、自動化・IoT技術を実運用展示
東京・江東区に最先端物流センター開設
日本通運は東京・江東区新砂に、IT化や自動化、可視化などを目的とした最新物流システム機器・設備と同社のオペレーションを一体化させた物流ソリューションを集約させた最先端ロジスティクスセンター「NEX-Auto Logistics Facility」を新設する。今年6月の開設予定だ。
物流現場で自動化・省人化設備の導入が求められる中、先端物流機器の導入には、最適な機器の選定、大規模なレイアウト変更、作業フローの見直しのほか、投資資金負担などの諸課題をクリアする必要がある。日通は顧客にとって最適な最先端の物流機器と、同社の「現場力」を融合した新しいソリューション「NEX-Sustainable Logistics on NewStyle」としてシェアリングサービスなどの実現により、お客さまのロジスティクスに関する課題解決に向けた、物流ソリューションを提供していく。
今回の新センター開設には、そうしたソリューションを提示・提案するためのショールームの機能を持たせた。自動倉庫型ピッキングシステム「AutoStore(オートストア)」や最新の自動荷役機器、デジタルピッキングシステム、ITソリューションなどを導入。実際の業務をベースとしたモデルケースを構築。プレゼンルーム、研修センターとしての機能も持たせ、日通の高度なロジスティクスサービスの提供、販売、研究、教育の場として活用していく。
新センターは同社国内最大級の都市型物流拠点「Tokyo C-NEX」に隣接する施設「新砂5号」の3階部分(約3000平方メートル)に開設する。導入する最先端機器・設備は表の通り。今回の機器選定にあたっては、(1)省人化の推進(2)機器同士の接続を重視したという。(1)については、倉庫作業の完全自動化やAI(人工知能)を用いた物流ソリューションへの移行を見据えてのもの。従来は作業スタッフをサポートする機器の導入を進めてきたが、省人化を大く進める機器を採り入れ、半自動化倉庫を実現する。
(2)については、自動化マテハン機器を組み合わせた倉庫オペレーションの構築につなげる考え。倉庫作業の最新事例として、ロボットや自動倉庫の導入事例は出てきているものの、まだそれらを組み合わせて入庫から保管、仕分け、出庫までのフローを構築しているものは少ない。新センターの出庫作業では、オートストアとピッキングシステムのEVE、デジタルピッキングを組み合わせ、効率的かつ省人化した作業フローを構築している。
機器・設備のほか、日通商事や日通総合研究所、ワンビシアーカイブズのグループ会社のノウハウやサービスも組み合わせて、ソリューション、オペレーションを構築。日通総研が提供するデータ集計・分析ツール「ろじたん」や、ワンビシアーカイブズの現場改善プログラムなどを用いて、業務自体の高度化も推進する。ショールームにはグループ会社の紹介コーナーも設置。日通とグループ各社のソリューションを合わせ、お客さまからの相談受付、物流課題を解決する場としても機能させていくとしている。
今回は、アパレル物流に適した高度化・省人化ソリューションを整えたが、施設での取り組みをベースとして、他の産業・品目での先端・次世代物流の研究・構築、営業提案などを進めていく考え。また、次の展開として、新設備の導入やAIを活用した新たなソリューション構築も検討していくという。
■日通NECロジスティクス
電機精密で顧客物流業務取り込み
日通NECロジスティクスは、日本通運と連携し、NECの生産・販売物流で培ったノウハウをもとに半導体業界を中心とした電機精密業界の顧客の物流アウトソース需要の取り込みを進めている。
同社では、大手半導体メーカーの工場内の物流業務を長年受託している実績があり、生産領域に関わるノウハウを蓄積。これらノウハウに加え、半導体産業で求められる温湿度対策、防塵・静電気対策やクリーンルーム・保安基準などの施設環境や製品取り扱いに関わる高度高品質な運用手法を整備。また、これら手法に加え、同社独自で構築している幹線ネットワーク網での輸送を組み合わせることで半導体物流プラットフォームを確立した。
このプラットフォームを活用し、調達・生産・販売まで一貫での受託を進め、日本国内はもとより海外においても10カ国・地域でサービスを展開している。日本基準のトレーニングを受けた専任スタッフが教育・運用管理・改善活動を行い、日本品質で半導体の保管・出荷・配送需要に応えている。
さらに海外では、高付加価値なサービスとして、現地に法人や拠点を持たないが、いち早くビジネスを立ち上げたいという顧客に対し、非居住者VMI(ベンダー管理在庫)サービスの提案を進めている。同サービスにより顧客は生産拠点の移管や販売先国の変更などに素早く対応できるのがメリットだ。
また、前述の幹線ネットワークの活用という点では、国内において「展開物流」と呼ぶ多店舗・拠点への一括納入サービスにも注力。全国・地域など広域の複数拠点に「指定された期限内に画一化された製品群とサービス」で機器類の事前設定から納品・設置・回収までを行うサービスだ。パソコンをはじめ、コンビニのATMやPOSから駅施設の専用端末など、多様な機器を扱っている。同社の輸送ネットワークは、長年にわたり電機精密機器を扱うことで培った高い品質に加え、13年に日通グループとなってから、輸送網を強化。また日通グループのアセット・機動力を活用することで、全国各地で一斉納入・回収したいというニーズに応えられる体制が構築されている。
■商船三井ロジスティクス
海外各地で物流立ち上げ支援
商船三井ロジスティクスは海外各地での保管・配送などの物流立ち上げを得意とする。日本本社のロジスティクスソリューション(LS)部に機能を集約することで、スピーディーかつ高品質なオペレーション体制が構築できる仕組みを整えている。直近では、完成車の整備・点検など付加価値サービスのラインナップも拡充。フォワーディング事業で培ったネットワークを生かし、新興国・地域を中心に事業拡大を狙う。
コントラクトロジスティクス案件では、用地の選定から、スペースや要員の確保、オペレーション構築、その後の運営まで一貫したサポートを提供。LS部の保坂直輝部長は「ニーズに対して、テーラーメイドな物流を作り込めるのが強みだ」と話す。
海外、特に新興国でのロジスティクス構築では現地での人材育成が肝要となる。同社はLS部にノウハウを集中させていることで、世界各地どこでも作業手順書(SOP)やチェック体制の作り込み、作業員への教育・訓練などを確実かつ迅速に行える体制となっている。
付加価値サービスの提供にも力を入れる。昨秋にはフィリピンで大手自動車メーカーの完成車に関わる納車前点検(Pre-Delivery Inspection Center:PDI)サービスの取り扱いを開始した。センターを設け、輸入完成車に関わる水漏れテスト、軽微な修理や塗装、洗車などを含めた高品質なPDIサービスを、輸入通関、一時保管サービスとともに提供している。保坂部長は「自動車産業は裾野も広く、今後も拡大していきたい分野だ。商船三井の自動車船部隊とも連携し、PDIだけでなくサービスパーツなどの部品物流分野の業務にも取り組んでいきたい」と意気込む。
PDIのみならず品目やサービス内容にも広がりが出ている。昨年には米国西海岸で、販売店に納めるコンシューマー商材の取り扱いを開始。自営倉庫を利用し、数千におよぶ細かなアイテムの在庫管理、キッティング、国内出荷(店舗配送およびeコマース)を手掛けている。また直近では、インドネシアのスマトラ島で機械製品の保管・域内配送業務を受託した。部品物流に加え、消費財の取り扱いや、新興地域での国内・域内配送といった分野での拡大も進めていきたいとの意向だ。
■横須賀港
来年、新門司とのフェリー航路新設へ
横須賀港は来年、北九州港・新門司地区との国内フェリー航路が就航する予定だ。国内外でフェリー事業を展開するSHKライングループが運航する計画で、同グループは昨年4月に運航会社として東京九州フェリーを設立。約1万6000総トン級のフェリー2隻を投入し、日曜を除く週6便体制で運航する。片道20時間半と高速輸送体制を構築しており、九州へ迅速な荷物の輸送が可能となる。横須賀市は物流・観光両面での利用促進活動を積極化するとともに、今後、関係機関や事業者などと協議を行い、必要経費を予算に盛り込む方向で調整する。就航に備えて関係する整備を進めていく方針だ。
横須賀港としては国内フェリーの就航に加え、久里浜地区への定期航路の誘致も狙う考えだ。同地区では現在、東京湾フェリーや離島行きの観光船が就航しているが、定期的な貨物航路はシャトルハイウェイラインによる横須賀-大分航路が2007年に休止して以降、存在していなかった。久里浜港地区は東京湾入口に位置するため、浦賀水道航路の速度制限を受けないほか、混雑する都心を通らずに東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道にアクセス可能というメリットがある。今後も圏央道の藤沢-釜利谷間が開通する予定で、北関東方面へのアクセスも改善される。背後圏への輸送利便性を強みに新規船社の誘致を図っていきたい考えだ。