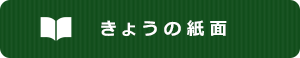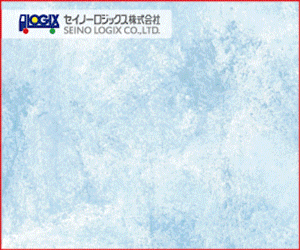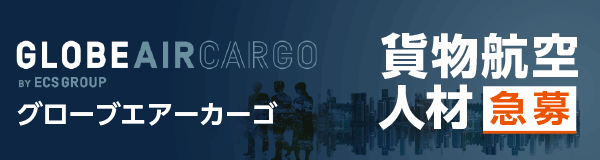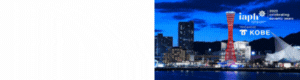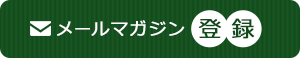- ニュース
- コラム
コラム
2011年5月6日
【展望台】どう取り組む夏の節電
福島原発事故の収束に向けていまだ見通しが立たない中、夏の電力不足は避けられそうにない。東京電力は、今夏の供給能力を4650万キロワット、午後1~3時のピーク需要は、節電効果を織り…続き
2011年5月2日
【展望台】海外生産移転は進むか
東日本大震災の影響で注目される一つが、海外への生産シフトだ。この見通しの背景には「震災を機に、一挙にメード・イン・マーケットを加速させる」というものだ。目下、記者が知り得る限り顕…続き
2011年4月28日
【展望台】「特需」にまつわる臆病風
「地元の建設会社は『震災特需』と言って大騒ぎだよ」。福島県の浜通りにいる友人が、そんなことを言っていた。もともと若年層の流出が止まらず、地場経済は縮小の一途だった。そこに100年…続き
2011年4月28日
【ロジスティシャンノ四方山話】(13)天動説・地動説を知っていますか 栂尾武幸 実運送業者は総合物流足り得ず
1987年の暮れごろのことだが、米国のオープンスカイに続いて新海事法が施行された。それまで同盟船社がコンテナ輸送の主力をなしていた市場に、その同盟船社が使い古した船を使って安い運…続き
2011年4月27日
【展望台】復興支援に土産を買った
先日、国内線が再開したばかりの仙台空港に行った。被災から1カ月余り、途絶えていた空路復活を機に、空港周辺の被災および回復状況を見て回った。着いた旅客ターミナルビルは、停電したまま…続き
2011年4月27日
【関西だより】震災後の関西経済の今後
極めて広域にマイナス影響を及ぼしている東日本大震災後において、長らく2割経済と称され、関東の後塵を拝してきた関西(経済)の機能、役割が注目され出している。関西経済連合会も11年度…続き
2011年4月26日
【展望台】明日を変えるきっかけに
東日本大震災の発生後、テレビや新聞の報道で自衛隊や在日米軍の活躍、津波の襲来を6分遅らせたという世界最深の釜石の防波堤の話は、いろいろと考えさせられる内容だった。 釜石市で…続き
2011年4月26日
【空を飛んで海を知って 航海士めざす元航空パイロット】(中) アメリカの力を再認識 森 充
[試験にみる実用性] 海技試験とも関わるが、海上交通安全法の「航路ごとの航法」、あるいは港則法の「航路及び航法」に相当するような部分は、航空では直接に学科試験(ATR=定期運…続き
2011年4月25日
【展望台】「複合震災」に立ち向かえ
東日本地域の物流インフラに、壊滅的な被害をもたらした東日本大震災が発生してから約1カ月半が経過した。物流業界では、国内外からの支援、そして被災者側自らの「何としても復興してみせる…続き
2011年4月22日
【展望台】フクシマ以後に詩を書く
医者から聞いた話だが、ぜんそくの発作が増えているという。花粉の影響だけでなく、震災関係の不安要素でストレスがたまって体調を崩し、そこから誘発されるケースがあるそうだ。それかどうか…続き
2011年4月22日
【物流つれづれ話】(38)岩崎 仁志 新入社員を育てるには やってみせ、させてほめるが力に
前号で人材育成について語った。今回はその中で、新入社員の育成について考察する。4月1日を迎え、多くの会社に新入社員が入社、希望に胸を膨らませているはずであった。しかし物流業に限ら…続き
2011年4月21日
【展望台】乗員訓練が始まった787
全日本空輸が18日から、ボーイング787型機の乗員訓練を開始した。787型機はボーイング社(以下ボ社)が開発中の最新鋭旅客機で、全日空はそのローンチカスタマーだ。訓練は全日空とボ…続き
2011年4月21日
【ロジスティシャンの四方山話】(12) 原発第1号機を扱って (下) 栂尾武幸 難問クリアし航空輸送実現
当時はまだ大阪・伊丹空港に貨物機は直行していないため東京のフライングタイガー(FT)を通じ定期便のFT機をチャーター便ルールを運用し伊丹空港にダイバートする許可を航空局より取り付…続き
2011年4月20日
【展望台】再興の歩み伝えていく
東日本大震災から1カ月余。震度6規模の余震が続く。「心が萎(な)える」。ようやく復旧した電気と上下水道が再び停止した避難所から、被災者の声が伝えられる。当然の心情だ。察するに余り…続き
2011年4月20日
【地球見聞録】マニラの元気な子どもたち 川崎汽船マニラ駐在員事務所 寺西勝己 日本人から笑顔教わった、と
1995年から2000年の間、タイのバンコクで駐在を経験し、今回が2回目の海外勤務となりました。社命はマニラ駐在。10年10月、再び東南アジアの地にやって来ました。バンコク駐在時…続き
2011年4月19日
【展望台】大震災後の思想の転回
今から250年以上も昔、西欧の広い範囲で大地震が起きた。死者は6万人とも10万人とも伝えられるが、とりわけポルトガル・リスボンの被害が甚大だったため今日では「リスボン大地震」と呼…続き
2011年4月19日
【空を飛んで海を知って 航海士めざす元航空パイロット】(上) 華麗にも“加齢”なる転身 森充
日本航空のパイロットを38年間努めて2007年に定年退職した後、東海大学航海学科に入学し航海士の勉強中である森充氏。まさに空から海への大旋回で、ダイナミックな人生を続行中だが、航…続き
2011年4月18日
【展望台】物流リスク再点検必要
東日本大震災で東北地方の生産拠点が被災し、世界中で部品不足による生産活動の停滞が起きている。サプライチェーンの混乱は製品分野を問わず国内外のメーカーに及んでおり、改めて日本から世…続き
2011年4月15日
【展望台】有事に強い空港運営を
「現在、大規模な地震に対しても耐震性が確保されている空港の割合は14%、緊急輸送に活用できる空港が100キロ圏域内にある人口の割合は38%に過ぎないが、これを早期に向上させる必要…続き
2011年4月14日
【展望台】夢のあるプレーに期待
「カーン」という音が鳴り響く。観客の歓声や視線で打球の行方を想像し、場の雰囲気を察知する。グラウンドに注がれる観客の視線を妨げないように注意しながら観客の視線を誘う。 特別…続き